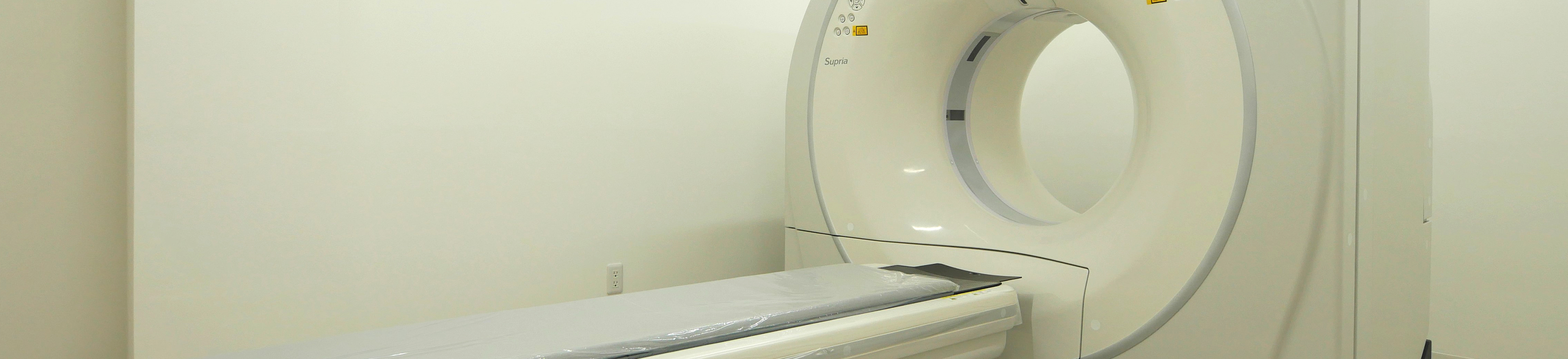
脳神経内科DEPARTMENT OF NEUROLOGY
「運動機能」や
「記憶」などに
関わる病気を
幅広く診療
「脳神経内科」は一般的にはあまりなじみのない科目だと思いますが、脳や脊髄、末梢神経、筋肉の病気を幅広く診療しています。
症状としては、しびれ、めまい、手足の力が入らない、歩きにくい、しゃべりにくい、頭痛、もの忘れ、手足や身体が勝手に動いてしまうなど、おもに「運動機能」や「記憶」「認知」などにまつわるさまざまな不調が対象になります。
全身を診療できることが特徴ですが、心や精神的な病気を扱う「精神神経科」や「神経科」とは異なります。

このような症状は脳神経内科に
ご相談ください
- 頭痛、めまい
- もの忘れが多くなった
- 手足がしびれる、ふるえる、
勝手に動いてしまう - 歩きにくい、転びやすい
- しゃべりにくい、言葉が出ない
- 飲み込みにくい、よくむせる
- 顔やまぶた、手足がけいれんする
- 眠れない
- 脳卒中の後遺症
- 意識障害
日本神経学会専門医・日本認知症学会専門医による診療

当院の院長は脳神経や認知症の専門医の資格を保有し、特に脳卒中の再発予防と認知症の診療に力を入れています。
また、脳神経内科は全身を診ることができるため、診断結果によっては整形外科や脳神経外科、精神科などの適切な科をご紹介できます。「何科を受診したらよいかわからない」という場合もお気軽にお問い合わせください。
当院では専門知識を活かした適切な診査・診断と、名古屋市の大学病院や総合病院との連携体制によって病気の早期発見と早期治療に努め、手術後のフォローアップなどもいたします。
脳卒中の予防・
継続治療
脳卒中(脳血管障害)とは、おもに脳の血管が詰まる「脳梗塞」、血管が破れる「脳出血」「くも膜下出血」によって、脳機能がダメージを受ける病気の総称です。脳卒中を発症した方は一刻も早く、大学病院などの大きな病院で手術や血栓の融解などの「急性期の治療」を受ける必要があります。
その後はリハビリを行いながら、再発予防のために治療を継続します。当院では、急性期の治療後のフォローアップと再発予防を行っています。

脳卒中と生活習慣病の関係
脳卒中は「動脈硬化」によって発症リスクが増大します。動脈硬化とは血管が硬く、細く、そしてもろくなってしまう状態で、老化だけでなく高血圧症、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病によって進行します。
つまり、脳卒中の再発予防には生活習慣病のコントロールが欠かせません。脳梗塞の患者さまには、生活習慣病の改善とあわせて、血液をサラサラにするお薬も服用していただきます。
患者さまがなるべくストレスや負担を感じずに病気と上手に付き合っていけるように、お一人お一人の生活背景なども考慮したきめ細やかな治療をご提案いたします。
頭痛の治療・予防
「自分は頭痛持ちだから」と治療をあきらめていたり、「たかが頭痛」と放置していませんか?
頭痛は誰もが日常的に発する症状なので、あまり気にしない人も多いでしょう。しかし、頭痛を甘く見てはいけません。
ただの頭痛と思っていたら、実は大きな病気の前兆やサインだったということもあるのです。時には命に関わったり、重篤な後遺症を残したりする場合もあるため、以下のような頭痛であればなるべく早めの受診をおすすめします。

注意が必要な頭痛
- 突然、今まで経験したことのない
痛みを感じる - 頻度が増え、痛みも強くなっている
- 50歳以降に始まった
- うまく歩けない、しゃべれない、
物が二重に見えるなどの症状を伴っている - がんや免疫不全の持病がある
- 発熱や首が前に曲がりにくいなどの症状を伴っている
もの忘れ・認知症

もの忘れは、加齢に伴って誰にでも起こることです。しかし、認知症の初期症状や脳疾患から起こるもの忘れもあるため注意が必要です。
残念ながら、自分自身で「加齢による心配のないもの忘れ」と「認知症や脳疾患による早期治療を要するもの忘れ」を見分けることは非常に難しいといわれています。そのため、ご家族をはじめ周りの方が「同じ話を何度も繰り返す」「食べたことを忘れる」「趣味などへの意欲がなくなった」といったサインに気づいてあげることが大切です。当院では、ご本人はもちろんご家族からのご相談も承っております。
加齢・認知症・脳の病気による
「もの忘れ」
-
加齢によるもの忘れの特徴
- もの忘れの自覚がある
- 細部は忘れていても、体験したこと自体は覚えている
- 昔から行っている家事や作業などは問題なくできる
- 物事の適切・不適切の判断はできる
-
認知症によるもの忘れの特徴
- もの忘れを自覚できていない
- 体験した出来事そのものを忘れている
- 今までできていた料理や作業などに支障が出る
- 物事の適切・不適切の判断ができない
-
脳疾患によるもの忘れの特徴
脳腫瘍などの脳疾患によって、もの忘れが起こることがあります。MRI検査やCT検査によって原因がわかれば、適切な治療により症状の改善も望めます。もの忘れ以外に以下のような症状がある場合は、すぐに専門医を受診するようにしましょう。脳疾患の種類によって、もの忘れに伴う症状も異なります。
- 言葉が出にくい
- しびれ・麻痺
- 頭痛
- 吐き気・嘔吐
- 片目だけ視野が欠損するなどの
視野異常 - 身体の片側にだけ麻痺がある
- けいれん
- 歩くとフラフラする、歩行障害
- 尿失禁
手足のふるえ

緊張や寒さを感じていないにも関わらず、手足や頭、声にふるえが現れる場合は病気の可能性があります。パーキンソン病・甲状腺機能亢進症(バセドウ病)・肝性脳症など、ふるえを引き起こす病気は複数あるため、早めに脳神経内科で適切な診断を受けることが大切です。
ふるえの原因となる疾患
-
パーキンソン病
パーキンソン病のふるえはじっとしているときに起こりやすく、規則正しく小刻みにふるえることが特徴です。 パーキンソン病はふるえ以外にも、うまく歩けない(歩行障害)、動きが遅くなるなどの症状が出ます。脳神経内科での適切な診断・治療が必要です。
-
本態性振戦(ほんたいせいしんせん)
40歳以上の方に多く見られるふるえです。文字を書いたり、コップを持ったりするときに現れやすく、おもに手・頭・声がふるえます。「本態性」とは原因不明という意味で、特に病気によるものではありません。しかし、日常生活に支障が出る場合は薬による治療も可能です。
-
甲状腺機能亢進症(バセドウ病)
甲状腺ホルモンが過剰に分泌されて起こる病気です。動悸、多汗、眼球突出などの症状のほか、手の細かなふるえが現れることがあります。
